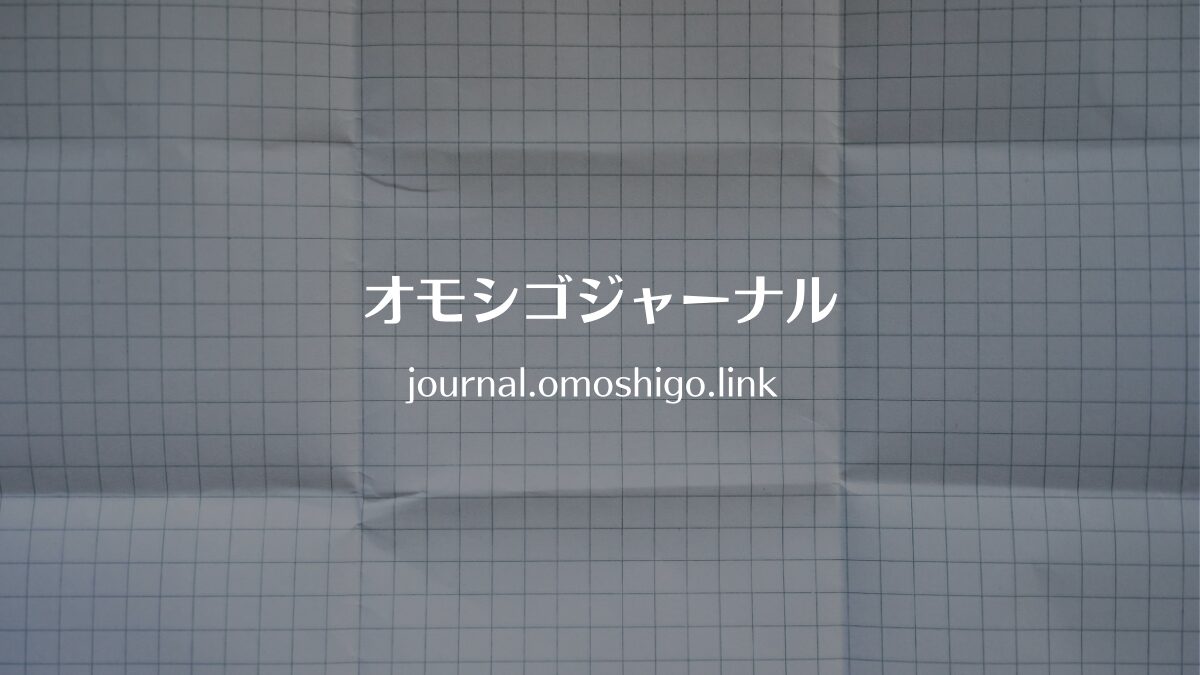「複業を始めたいけど、どの企業が解禁しているの?」「将来のキャリアに複業はどう影響するの?」そんな疑問を持つビジネスパーソンが増えています。本記事では、2025年最新の複業解禁企業55社のリストと、複業を活かしたキャリア戦略について徹底解説します。転職市場で評価される複業経験や、企業が複業を解禁する本当の理由まで、あなたのキャリアの可能性を広げる情報をお届けします。
複業解禁の現状:企業が注目する新しい働き方
2025年、日本企業の中でも複業・副業を解禁または容認する時代となりました。この動きは2018年の厚生労働省による「副業・兼業の促進に関するガイドライン」公表を契機に加速し、現在では大手企業を中心に複業を積極的に推進する流れが定着しています。
特に注目すべきは、単なる「副業解禁」から「複業推奨」へとシフトしている点です。従来の副業は本業の片手間という位置づけでしたが、複業は複数の仕事を並列で行い、それぞれを本業として捉える考え方です。パナソニックやサイボウズなどの先進企業では、社員の複業を通じたスキルアップやイノベーション創出を企業成長の源泉と位置づけています。
企業側の懸念だった「人材流出」「情報漏洩」「労働時間管理」の問題も、実際には杞憂であることが証明されつつあります。キリンホールディングスの事例では、複業を通じて「本業でまだやれることは多い」と再認識する社員が多く、むしろ定着率向上につながっています。
さらに特筆すべきは、三井住友海上火災保険のように「2030年を目安に複業経験を課長昇進の条件にする」と明言する企業も登場していることです。複業経験が単なる副収入源ではなく、キャリア形成の重要要素として評価される時代が到来しているのです。
複業を積極的に推進する先進企業TOP10
複業推進のトップランナーとして注目すべき企業10社を紹介します。これらの企業は単に複業を「許可」するだけでなく、社員の複業を「奨励」する制度や文化を確立しています。
- サイボウズ株式会社:「100人100通りの働き方」を掲げ、複業を強力に推進。複業経験を社内で共有する場を設け、本業へのフィードバックを促進しています。
- メルカリ:複業を「副業」ではなく「複業」と明確に位置づけ、「複業デー」という休暇制度を導入。社員の複業活動を積極的に支援し、社内での複業報告会も開催しています。
- ロート製薬:2016年という早い段階から複業を解禁した先駆者。社員の自己実現を支援する「複業」という概念を広めた功績は大きいでしょう。
- パナソニック:週休3日制度と複業制度を連動させ、副業収入の上限も撤廃。社員がより自由に外部での活動に取り組める環境を整備しています。
- 凸版印刷:45歳以上の社員を対象に通常勤務時間内での複業を認める「セカンドキャリア複業制度」を導入。中高年層の新たなキャリア構築を支援しています。
- 日本郵政グループ:週1日分の勤務を自治体や企業での複業に充てることを認める制度を導入。約6000人の社員が対象で、地域開発への貢献も視野に入れています。
- 塩野義製薬:全社員の7割を対象に週休3日制度と複業解禁を同時に実施。大学院でのリスキリングなども想定し、組織全体のイノベーション力強化を目指しています。
- DeNA:複業経験を社内で共有する仕組みを構築。最新技術や市場動向の知見を組織全体に還元する文化を醸成しています。
- ヤフー:副業に制限を設けず、出勤不要の働き方や週休3日制度も導入。「個々のウェルビーイングが高まれば業務パフォーマンスを最大化できる」という考え方を実践しています。
- ZOZOテクノロジーズ:週3日は本業、週2日は別会社で働くといった柔軟な働き方も可能にする制度を導入。複業を通じた技術者のスキルアップを促進しています。
これらの企業に共通するのは、複業を単なる「副収入源」ではなく、「キャリア形成」や「イノベーション創出」の手段として戦略的に位置づけている点です。複業解禁は人材確保の手段であると同時に、組織の変革を促進する経営戦略でもあるのです。
複業解禁のメリットと企業が期待する効果
企業が複業を解禁・推奨する背景には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主に以下の5つの効果が期待されています。
1. 優秀な人材の確保と定着率向上
ある調査によれば、約9割のビジネスパーソンが「副業禁止の会社には入社・所属したくない」と考えているという結果があります。複業解禁は優秀な人材を惹きつけるための必須条件になりつつあるのです。また、キリンホールディングスの事例のように、複業を通じて本業の価値を再認識する社員が多く、結果的に定着率向上につながっています。
2. 社員のスキルアップとイノベーション促進
社員が複業を通じて外部の知識や技術、最新トレンドに触れることで、本業でも新しい視点やアイデアが生まれやすくなります。サイボウズでは複業経験者が新規事業を立ち上げるケースも多く、複業がイノベーションの源泉となっています。
3. 社内では獲得できない知見の導入
ひとつの組織内では得られない多様な経験や人脈を社員が獲得することで、オープンイノベーションが生まれやすい環境が構築されます。特にDX推進やデジタルスキル習得において、複業経験が大きく貢献しています。
4. 社員のウェルビーイング向上
ヤフーのように「個々のウェルビーイングが高まれば業務パフォーマンスを最大化できる」という考え方が広がっています。複業を通じて自己実現や社会貢献を果たすことで、社員の満足度や幸福度が向上し、結果的に本業のパフォーマンスも上がるという好循環が期待できます。
5. リスキリングの実践の場の提供
学び直しが叫ばれる現代において、複業は新たに獲得したスキルを実践する絶好の機会となります。塩野義製薬のように大学院でのリスキリングと複業を組み合わせる取り組みも増えており、理論と実践の両面からスキルアップが可能になります。
ただし重要なのは、複業を解禁する目的を企業が明確に示し、社員も目的意識を持って取り組むことです。単に「トレンドだから」という理由での導入では、期待する効果は得られないでしょう。
複業を始める際の注意点とガイドライン
複業を始める際には、いくつかの重要な注意点とガイドラインを押さえておく必要があります。
就業規則の確認は必須
まず最初に行うべきは、自社の就業規則の確認です。厚生労働省が2018年に発表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では原則として従業員の副業・兼業を認めることが妥当と明記されていますが、各企業の就業規則によって条件は異なります。
一般的な複業解禁企業の条件には以下のようなものがあります:
- 事前申請または届出制であること
- 本業の業務に支障をきたさないこと
- 競合他社や利益相反となる企業での就業は不可
- 就業時間外や休日のみの活動に限る
- 健康管理に十分配慮すること
税金と社会保険の手続き
複業によって所得が増えると、確定申告が必要になるケースがほとんどです。給与所得と事業所得の区分や、経費計上の方法など、税務上の知識を事前に身につけておくことをおすすめします。また、社会保険料の取り扱いについても理解しておくことが重要です。
労働時間の適切な管理
複業による過重労働は健康リスクを高めるだけでなく、本業のパフォーマンス低下にもつながります。労働基準法では1日8時間、週40時間の労働時間制限がありますが、これは複数の事業場での労働時間を合算したものではありません。しかし、健康管理の観点からは総労働時間を適切に管理することが重要です。
情報管理の徹底
複業先と本業の情報を適切に管理することは極めて重要です。守秘義務や機密情報の取り扱いについては特に注意が必要で、本業と複業先の双方に迷惑をかけないよう、情報の区分管理を徹底しましょう。
目的を明確にする
複業を始める際には、「なぜ複業をするのか」という目的を明確にすることが成功の鍵です。単に収入増加を目指すのか、新しいスキルを獲得したいのか、将来の独立に向けた準備なのか、目的によって複業先の選び方や取り組み方は大きく変わります。東洋大学の川上淳之教授の研究によれば、スキル向上を目的とする人は満足感や幸福度が比較的高く、単に収入目的の人は低い傾向にあるとのことです。
複業を成功させるためのキャリア戦略
複業を単なる副収入源ではなく、キャリア戦略として活用するためのポイントを解説します。
本業と複業の相乗効果を最大化する
最も効果的な複業は、本業と複業が相互に良い影響を与え合う関係です。例えば、本業でマーケティングを担当しているなら、複業でも異なる業界のマーケティングに携わることで、多様な視点や手法を学べます。あるいは本業とは全く異なる分野に挑戦することで、新たな発想や視点を獲得することも可能です。
サイボウズの事例では、複業経験から新規事業を立ち上げた社員が、本業に新たな価値をもたらしています。このように複業で得た知見やスキルを本業に還元することで、キャリアの幅と深さを同時に広げることができます。
将来的な資産として積み上がるスキルを選ぶ
複業を選ぶ際は、将来的に資産として積み上がるかどうかを考慮することが重要です。資産とはスキルや人脈、経験など、長期的に価値を生み出すものを指します。例えば、特定の業界知識やプログラミングスキルなど、汎用性が高く需要が増加している分野を選ぶと良いでしょう。
三井住友海上火災保険のように複業経験が昇進条件になる企業も登場していることから、複業経験自体がキャリアの武器になる時代が来ています。
複業のための時間管理術を習得する
複業を成功させる上で最大の課題は時間管理です。本業と複業の両立には効率的な時間の使い方が不可欠です。タイムブロッキングやポモドーロテクニックなどの時間管理術を習得し、メリハリをつけた働き方を心がけましょう。
パナソニックや塩野義製薬のように週休3日制度と複業を組み合わせる企業が増えていることからも、ワークライフバランスを保ちながら複業に取り組める環境が整いつつあります。
複業コミュニティへの参加
複業経験者とのネットワーキングは貴重な情報源となります。メルカリやDeNAなどでは社内で複業報告会を開催していますが、社外のコミュニティに参加することも有益です。複業に関する情報交換や悩み相談ができるだけでなく、新たな複業機会につながる可能性もあります。
定期的な振り返りと軌道修正
複業を始めたら、定期的に振り返りの時間を設け、当初の目的に沿った活動ができているかを確認しましょう。必要に応じて複業の内容や時間配分を調整し、本業と複業のバランスを最適化することが長期的な成功につながります。
業界別・職種別の複業解禁トレンド
業界や職種によって複業解禁の状況や特徴は大きく異なります。2025年現在の主なトレンドを見ていきましょう。
IT・通信業界
IT業界は複業解禁の先駆けとなった業界です。メルカリ、DeNA、サイボウズなどのIT企業は早くから複業を推奨し、社内制度も充実しています。技術革新のスピードが速いこの業界では、複業を通じて最新技術に触れることが本業にも良い影響をもたらすと考えられています。
2024年にはNTT東日本とNTT西日本も複業解禁に踏み切り、大手通信会社でも複業解禁の流れが加速しています。
金融業界
従来は副業に厳しい姿勢だった金融業界ですが、近年は大きく変化しています。2022年3月末時点で40社以上の金融機関が副業を解禁し、その数は増加傾向にあります。鹿児島銀行では行員約2200人の調査で約8割が「副業する機会があればチャレンジしたい」と回答するなど、意欲の高まりが見られます。
銀行員の中には花火師やウェブデザイナーなど、本業とは全く異なる分野で複業を行う事例も登場しており、地域貢献や自己実現の手段として複業が活用されています。
小売・サービス業界
ファーストリテイリングやセブン&アイなどの大手小売チェーンでも複業解禁の動きが広がっています。特に店舗運営の経験を活かした接客コンサルティングなどの複業が人気です。
また、旅行業界でもエイチ・アイ・エスやJTBが複業を解禁し、観光に関する知識を活かした複業が奨励されています。
建設・不動産業界
大和ハウス工業では建築士の資格を持つ社員が個人で設計業務を行うことを認めるなど、専門性を活かした複業を推進しています。建設業界では技術者不足が課題となっており、複業を通じた技術者の確保や育成が進められています。
公務員・行政分野
公務員の複業は法律上の制限がありますが、各自治体が独自の規則を設けて一部容認する動きが広がっています。長野県では農産物の生産やスキーのインストラクター、地域課題解決に関連する事業の企画運営などを具体例として提示し、職員の複業を促進しています。
また、「行政複業」と呼ばれる、民間人材が複業として行政に参画する取り組みも増加しています。長崎県壱岐市では首都圏や福岡に在住の民間人材5名を複業アドバイザーとして採用し、ワーケーションの誘致や行政のDX化を進めています。
まとめ
2025年、複業解禁企業は着実に増加し、働き方の新たな選択肢として定着しつつあります。単なる副収入源としてではなく、キャリア形成やイノベーション創出の手段として複業を戦略的に活用する動きが広がっています。
複業を成功させるためには、本業と複業の相乗効果を意識し、将来的な資産として積み上がるスキルを選ぶことが重要です。また、時間管理や情報管理を徹底し、定期的な振り返りを行うことで、持続可能な複業キャリアを構築できるでしょう。
業界や職種によって複業の特性や可能性は異なりますが、どの分野においても「複業経験」自体が評価される時代が到来しています。三井住友海上火災保険のように複業経験を昇進条件にする企業も登場し、複業がキャリアの必須要素になりつつあるのです。
複業時代のキャリア戦略として最も重要なのは「自律」です。企業に依存するのではなく、自らのキャリアを主体的に設計し、複数の選択肢を持つことで、変化の激しい時代を生き抜く力を養いましょう。複業はその有効な手段の一つであり、今後ますます多くの人にとって「当たり前の働き方」になっていくことでしょう。
あなたも複業解禁企業のリストを参考に、自分に合った複業スタイルを見つけ、キャリアの可能性を広げてみませんか?