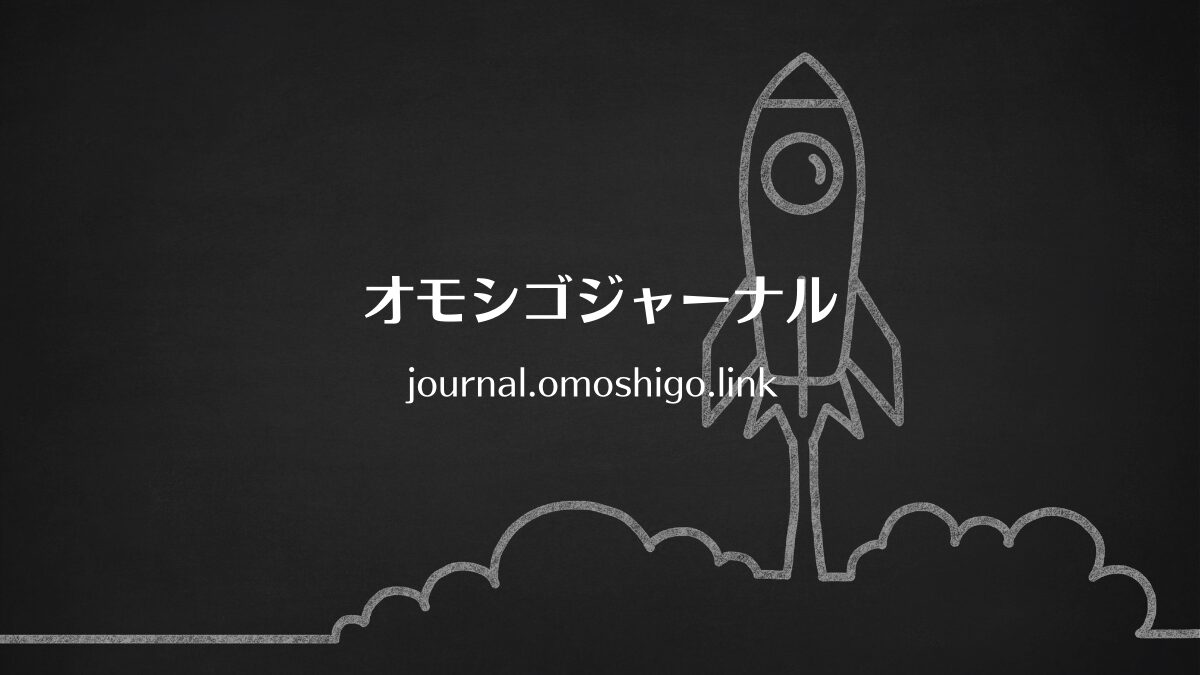DX化が進む現代において、リスキリングは企業成長に不可欠な要素となっています。
この記事では、リスキリングの基礎知識から、日本国内の企業における導入の成功事例までを詳しく解説します。
他社の具体的な取り組みをまとめた企業事例集を参考に、自社でのDX推進や人材育成を成功させるためのヒントを得ることが可能です。
そもそもリスキリングとは?DX時代に求められる新たな学び
リスキリングとは、デジタル化などの技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、従業員が新しいスキルや知識を習得する取り組みを指します。
DX時代において、企業が競争力を維持・向上させるためには、既存の業務内容にとらわれず、新たな価値を創出できる人材の育成が不可欠であり、その手段としてリスキリングが注目されています。
リスキリングの基本的な考え方を解説
リスキリングの基本的な考え方は、将来の事業戦略を見据え、今後必要となるスキルや知識を従業員に習得させることにあります。
これは単なるスキルアップとは異なり、新しい職務や役割を担うために必要な能力を体系的に身につけることを目的とします。
そのため、企業は自社の経営戦略に基づいて育成すべき人材像を定義し、それに沿った学習テーマや教育コンテンツを選定する必要があります。
例えば、DX推進をテーマとするならば、AIやデータサイエンス、クラウド技術といった分野のコンテンツが中心となります。
従業員が自律的に学習を進められるような環境を整備し、企業全体で学び続ける文化を醸成することが重要になります。
リカレント教育やOJTとは何が違うのか
リスキリングは、リカレント教育やOJTとしばしば混同されますが、その目的と主体が異なります。
リカレント教育は、個人がキャリアの中断などを経て、主体的に学び直すことを指すことが多いです。
これに対しリスキリングは、企業が主体となり、事業戦略上の必要性から従業員に新たなスキル習得を促す点に特徴があります。
また、OJT(On-the-JobTraining)は、既存の業務を遂行しながら、先輩社員の指導のもとで実践的にスキルを学ぶ教育手法です。
例えば、新しい営業手法を学ぶといったケースが該当します。
リスキリングは、現在の業務とは異なる、将来必要となる全く新しいスキルを習得する点に主眼が置かれており、その点でOJTとは区別されます。
多くの企業がリスキリングに注目する3つの背景
近年、多くの企業がリスキリングに注目している背景には、急速な社会変化が挙げられます。
特に、デジタル技術の進化は産業構造を大きく変え、企業に新たな対応を迫っています。
若手からベテランまで全従業員が変化に適応し、新しい価値を創造できる組織へと変革する必要性が高まっています。
デジタル化の加速でDX人材が不足している
デジタル化の急速な進展により、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が経営上の重要課題となっています。
しかし、AI、IoT、データサイエンスといった先進技術を扱える専門人材の需要が急増する一方で、供給が追いついていないのが現状です。
外部からの採用だけで必要な人材を確保することは困難であり、採用コストも高騰しています。
こうした状況から、自社の事業内容を深く理解している既存社員を対象にリスキリングを実施し、社内でDX人材を育成する動きが活発化しています。
このアプローチは、人材不足の解消だけでなく、従業員のキャリア開発や組織全体のデジタル対応能力の向上にも寄与します。
変化の激しい時代に対応できる組織作りが急務
現代はVUCA時代とも呼ばれ、市場環境や顧客ニーズが予測困難なほど激しく変化しています。
このような状況下で企業が持続的に成長するためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織作りが不可欠です。
特に、組織の中核を担う30代をはじめとする従業員が、既存のスキルや知識に固執せず、常に新しいことを学び続ける姿勢を持つことが重要になります。
リスキリングは、従業員に新たな視点やスキルをもたらし、変化への適応力を高める効果的な手段です。
組織全体で学習する文化を醸成し、従業員一人ひとりが自律的にキャリアを形成していける環境を整えることで、企業は不確実性の高い時代を乗り越えるための強固な基盤を築くことが可能となります。
既存社員のスキルアップで人材流出を防ぐ
従業員が自身のキャリア成長に不安を感じると、より良い機会を求めて離職してしまう可能性があります。
特に、自身のスキルが陳腐化することへの懸念は、優秀な人材の流出につながりかねません。
企業がリスキリングの機会を提供することは、従業員に対して成長を支援する姿勢を示すことになり、エンゲージメントの向上に直結します。
従業員は、会社から期待されていると感じ、自身の市場価値を高めることができるため、働く意欲が高まります。
結果として、定着率が向上し、企業は経験豊富で自社への理解が深い人材を維持できます。
このような好循環は、組織全体のパフォーマンス向上にも大きく貢献します。
企業がリスキリングに取り組むことで得られるメリット
企業がリスキリングに取り組むことで得られるメリットは多岐にわたります。
従業員のスキル向上による生産性向上はもちろん、新たなイノベーションの創出や組織全体の変革対応力の強化が期待できます。
最近では、企業の取り組みがレポートやメディアで紹介されることもあり、企業価値の向上にもつながっています。
従業員のスキル向上で生産性が高まる
リスキリングによって従業員が新たなデジタルツールやデータ分析のスキルを習得すると、これまで手作業で行っていた業務を自動化したり、データに基づいた的確な意思決定を下したりできるようになります。
これにより、業務プロセスが効率化され、一人ひとりの生産性が向上します。
例えば、営業担当者が顧客データを分析するスキルを身につければ、より効果的なアプローチが可能になり、成約率の向上が見込めます。
また、バックオフィス部門の従業員がRPA(RoboticProcessAutomation)を活用できるようになれば、定型業務にかかる時間を大幅に削減し、より付加価値の高い業務に集中できます。
このように、個々のスキルアップが組織全体の生産性向上に直結します。
新しい視点が生まれイノベーションを創出しやすくなる
従業員がリスキリングを通じて異分野の知識や最新の技術を学ぶと、従来の発想にとらわれない新しい視点を得ることができます。
これまで当たり前だと思っていた業務プロセスやビジネスモデルに対して、新たな切り口から改善案や新事業のアイデアが生まれやすくなります。
例えば、製造業の技術者がデータサイエンスを学ぶことで、製品開発に新たなアプローチを取り入れたり、品質管理の精度を飛躍的に向上させたりすることが可能になります。
異なるスキルを持つ従業員同士が協働することで、部門の垣根を越えたアイデアの融合が起こり、組織全体のイノベーション創出が促進されます。
社員のキャリア開発意欲を刺激しエンゲージメントが向上する
企業が従業員の学び直しを支援する姿勢を明確に示すことは、従業員のエンゲージメント向上に大きく貢献します。
リスキリングの機会が提供されることで、従業員は会社が自身の長期的なキャリア形成を支援してくれていると感じ、学習意欲が高まります。
自分のスキルが向上し、社内で新たな役割に挑戦できる可能性が広がることは、仕事への満足度や組織への帰属意識を高める効果があります。
また、自律的に学習し、キャリアを切り拓いていくという経験は、従業員の自信にもつながります。
結果として、従業員はより主体的に業務に取り組むようになり、組織全体の活性化が期待できます。
事業構造の変化に柔軟に対応できる組織になる
市場のニーズや技術のトレンドが急速に変化する現代において、企業が生き残るためには事業構造の変革が不可欠です。
リスキリングは、こうした変化に対応できる人材を内部で育成するための有効な手段となります。
例えば、主力事業が衰退し、新たな分野へ進出する必要が生じた際に、従業員が必要なスキルを習得していれば、スムーズな事業転換が可能になります。
外部から人材を採用するだけでなく、既存の従業員を再教育することで、企業文化や事業への深い理解を持つ人材を新たな領域で活用できます。
これにより、組織は環境変化に対するレジリエンス(回復力・適応力)を高め、持続的な成長を実現するための基盤を構築できます。
【DX推進】国内企業のリスキリング導入成功事例10選
国内でも多くの企業がDX推進を目的としたリスキリングに成功しています。
ここでは、製造業からIT、金融まで、多様な業界における具体的な他社事例を10件紹介します。
富士通やヤフーといった先進企業の取り組みをはじめ、各社がどのように課題を乗り越え、成果を出しているのかを知ることで、自社導入のヒントを得られます。
【製造業の事例】全社員を対象にAI・データ活用人材を育成
ある大手電機メーカーでは、全社員を対象とした大規模なリスキリングプログラムを実施しています。
目的は、AIやデータサイエンスのスキルを持つ人材を社内で育成し、全社的なDXを加速させることです。
プログラムは、リテラシーレベルから専門家レベルまで複数の階層に分かれており、従業員は自身の職種やスキルレベルに応じて受講できます。
オンライン学習プラットフォームを活用し、時間や場所にとらわれずに学習できる環境を整備しました。
この取り組みにより、製造現場ではデータ分析に基づく生産効率の改善が進み、開発部門ではAIを活用した新製品のアイデアが生まれるなど、具体的な成果が出始めています。
【IT企業の事例】営業職からDXコンサルタントへのキャリアチェンジを実現
ある大手IT企業では、従来の製品販売を中心としていた営業職の役割を、顧客のDX課題を解決するコンサルタントへと転換させるためのリスキリングに取り組んでいます。
このプログラムでは、営業担当者がクラウド技術、データ分析、セキュリティなどの専門知識を体系的に学びます。
座学だけでなく、実際のプロジェクトに参画し、OJT形式で実践的なスキルを磨く機会も提供されます。
これにより、顧客の業界知識や業務内容を深く理解している営業担当者が、テクノロジーの知見を掛け合わせることで、より付加価値の高い提案ができるようになりました。
結果として、大型案件の受注増加や顧客満足度の向上につながっています。
【金融機関の事例】非IT部門の社員が業務改善アプリを内製
あるメガバンクでは、非IT部門の従業員を対象に、ローコード・ノーコード開発ツールの活用スキルを習得させるリスキリングを実施しました。
目的は、現場の業務を最もよく知る従業員自身が、業務効率化のための簡単なアプリケーションを開発できるようにすることです。
研修を受けた従業員は、これまで手作業で行っていたデータ集計や報告書作成といった定型業務を自動化するアプリを次々と開発しました。
これにより、IT部門に開発を依頼することなく、現場レベルで迅速な業務改善が可能となりました。
結果として、全社的な生産性向上はもちろん、従業員のDXに対する意識改革や主体性の向上にもつながっています。
【通信会社の事例】5GやIoT分野の専門家を社内で育成
大手通信会社では、次世代通信規格である5GやIoT、AIといった先端技術分野の事業拡大を見据え、社内での専門家育成に力を入れています。
外部からの採用だけに頼るのではなく、既存の通信技術者を対象とした高度なリスキリングプログラムを構築しました。
このプログラムでは、大学や研究機関と連携し、最新の技術動向や専門知識を学べる機会を提供しています。
さらに、社内に実証実験環境を設け、学んだ知識をすぐに実践で試せる場を用意しました。
この取り組みにより、新規事業領域で中核を担う高度専門人材を安定的に確保し、企業の競争力強化に成功しています。
【商社の事例】データサイエンティスト育成プログラムを全社展開
総合商社では、データ駆動型経営への転換を目指し、データサイエンティストの育成プログラムを導入しました。
このプログラムは、文系・理系を問わず、データ活用に関心のある全従業員を対象としています。
統計学の基礎から機械学習の実装まで、段階的にスキルを習得できるカリキュラムが特徴です。
選抜されたメンバーは、通常業務から一時的に離れ、集中的に学習に取り組みます。
プログラム修了後は、各事業部門に戻り、データ分析の専門家として現場の課題解決を主導する役割を担います。
この結果、各部門でデータに基づいた意思決定が浸透し、新たなビジネスチャンスの創出にもつながっています。
【小売業の事例】店舗スタッフがECサイトのデータ分析を担当
ある大手小売企業では、実店舗とECサイトの連携強化(OMO)を推進するため、店舗スタッフを対象としたリスキリングを実施しています。
研修では、ECサイトのアクセス解析や購買データの分析手法を学び、データに基づいた顧客理解を深めることを目的とします。
研修を受けたスタッフは、顧客のオンラインでの行動履歴を参考に、実店舗での接客や商品提案に活かしています。
また、店舗での顧客の声をECサイトの品揃えやキャンペーン企画にフィードバックするなど、双方向の連携が生まれています。
これにより、顧客一人ひとりに最適化された購買体験の提供が可能となり、顧客満足度と売上の向上を実現しました。
【建設業の事例】現場技術者がドローンや3D CADスキルを習得
建設業界では、人手不足や生産性向上が喫緊の課題となっています。
ある建設会社では、現場の技術者を対象に、ドローン測量や3DCAD、BIM/CIMといったICT施工技術に関するリスキリングプログラムを導入しました。
これらのスキルを習得することで、測量にかかる時間を大幅に短縮したり、設計データを活用して施工の精度を高めたりすることが可能になります。
研修は、座学と実技を組み合わせて行われ、現場ですぐに活用できる実践的な内容となっています。
この取り組みにより、工事の生産性と安全性が向上し、若手技術者にとっては新しい技術を学ぶキャリアアップの機会となり、モチベーション向上にもつながっています。
【サービス業の事例】マーケティング部門のデジタルツール活用を促進
あるホテル運営会社では、顧客体験の向上を目指し、マーケティング部門のリスキリングに注力しています。
従来のマス広告中心の戦略から、デジタルマーケティングへと軸足を移すため、従業員にMA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客関係管理)システムの活用スキルを習得させました。
研修を通じて、顧客データの分析手法や、分析結果に基づいたパーソナライズドされたコミュニケーション施策の立案方法を学びます。
このサービスにより、宿泊客の属性や過去の利用履歴に応じた最適な情報提供が可能となり、リピート率の向上や顧客単価の上昇といった成果を上げました。
マーケティング活動のROI(投資対効果)も大幅に改善しています。
【食品メーカーの事例】工場のスマート化を推進する人材を育成
ある食品メーカーでは、生産性向上と品質管理の高度化を目指し、工場のスマート化を推進しています。
その一環として、製造ラインのオペレーターやエンジニアを対象に、IoT機器やセンサーから得られるデータを活用するためのリスキリングを実施しました。
プログラムでは、データ収集の基礎から、収集したデータの可視化、分析手法までを学びます。
スキルを習得した従業員は、生産設備の稼働状況をリアルタイムで監視し、異常の予兆を検知して事前に対策を講じることが可能になりました。
これにより、設備の突発的な停止を防ぎ、生産計画の安定化と製品品質の向上を実現しています。
【不動産業の事例】VR内覧など新技術に対応できる営業担当者を育成
不動産業界でもDXの波が押し寄せ、顧客の物件探しのスタイルも変化しています。
ある不動産会社では、VR(仮想現実)技術を活用したオンライン内覧サービスを導入するにあたり、営業担当者向けのリスキリングプログラムを開始しました。
この研修では、VRゴーグルの操作方法や効果的なオンラインでの物件案内のノウハウを学びます。
また、顧客データを分析し、オンラインでの反響が高い物件の特徴を把握するスキルも習得します。
これにより、遠隔地に住む顧客や多忙な顧客に対しても、時間や場所の制約なく物件を提案できるようになりました。
新たな営業スタイルに対応することで、商談機会の増加と成約率の向上に成功しています。
企業のリスキリング導入を成功に導く4つのポイント
リスキリングの導入を成功させるためには、単に研修を用意するだけでは不十分です。
企業の目指す方向性と連動したリスキリング戦略を策定し、従業員の意欲を引き出す具体的な施策を計画的に実行することが重要です。
ここでは、成功に導くための4つのポイントを解説します。
会社の経営戦略とリスキリングの目的を明確に連携させる
リスキリングを成功させる最初のステップは、自社の経営戦略や事業目標と、人材育成の方向性を明確に結びつけることです。
「DXを推進する」「新規事業を創出する」といった経営目標を達成するために、どのようなスキルを持つ人材が、いつまでに、何人必要なのかを具体的に定義します。
この目標が曖昧なままでは、どのようなスキルを習得させるべきかが定まらず、研修が単なる自己啓発で終わってしまう可能性があります。
経営層が主導し、将来の事業構想から逆算して育成計画を立てることが不可欠です。
従業員に対しても、なぜこのスキルを学ぶ必要があるのか、会社の将来にどう貢献するのかを丁寧に説明し、納得感を得ることが学習効果を高める上で重要となります。
従業員一人ひとりの学習意欲を引き出す仕組みを作る
従業員が自発的に学習に取り組むためには、意欲を引き出す仕組み作りが欠かせません。
例えば、学習時間の一部を業務時間として認定したり、スキル習得を人事評価や昇進・昇格の要件に組み込んだりすることが有効です。
また、学習の進捗状況を可視化し、上司や同僚と共有できるプラットフォームを用意することで、切磋琢磨する環境が生まれます。
学習成果を発表する場を設けたり、習得したスキルに応じてインセンティブを付与したりすることもモチベーション維持に繋がります。
重要なのは、会社が従業員の学びを本気で支援しているというメッセージを伝え、学習することが評価される文化を組織全体で醸成していくことです。
学んだスキルを実践で活かせる機会を提供する
研修で知識をインプットするだけでは、スキルは定着しにくいです。
学習した内容を実際の業務で活用する機会を意図的に提供することが極めて重要です。
例えば、データ分析の研修を受けた従業員には、実際の業務データを使った分析プロジェクトに参加させます。
プログラミングを学んだ従業員には、部署内の小規模なツール開発を任せるなど、具体的なアウトプットの場を用意します。
こうした実践経験を通じて、従業員はスキルの有用性を実感し、さらなる学習意欲を高めることができます。
また、現場で試行錯誤する中で、新たな課題や学びが生まれ、より深い理解へとつながっていきます。
学んだスキルが業務成果に直結する成功体験を積ませることが、リスキリングを定着させる鍵となります。
外部の研修サービスや助成金を効果的に活用する
自社内だけで全てのリスキリングプログラムを構築・運営するのは、多大なコストと労力がかかります。
特に、AIやデータサイエンスといった専門性の高い分野では、社内に指導できる人材がいないケースも多いです。
こうした場合は、外部の専門的な研修サービスやeラーニングプラットフォームを積極的に活用することが効率的です。
多様なプログラムの中から、自社の目的に合ったものを選択できます。
また、国や地方自治体が提供する人材開発支援助成金などを活用すれば、研修にかかる費用負担を軽減することも可能です。
これらの外部リソースを効果的に組み合わせることで、質の高い学習機会をより多くの従業員に提供でき、リスキリングの取り組みを加速させることができます。
リスキリング導入で企業が直面しやすい課題と対策
リスキリングの導入は多くの企業にとって重要な課題ですが、その過程で様々な壁に直面することも少なくありません。
計画通りに進まない、成果が出ないといった失敗を避けるためには、事前に起こりうる課題を想定し、対策を講じておくことが肝要です。
ここでは代表的な課題とその対策を解説します。
従業員の学習時間を確保するのが難しい
従業員がリスキリングに取り組む上で最大の障壁となるのが、通常業務に追われて学習時間を確保できないという問題です。
会社が学習を奨励しても、日々の業務負担が大きければ、従業員は学習を後回しにしがちになります。
この課題を解決するためには、経営層や管理職がリスキリングの重要性を理解し、組織として学習時間を確保するコミットメントを示す必要があります。
例えば、週に数時間を学習専用の時間として業務スケジュールに組み込んだり、学習期間中は一時的に業務量を調整したりするなどの配慮が求められます。
また、細切れの時間でも学習しやすいマイクロラーニング形式の教材を提供するなど、学習方法を工夫することも有効な対策となります。
学習効果が実際の業務に結びつかない
研修を受けて知識は得たものの、それが実際の業務改善や成果に結びつかないという課題も多く見られます。
これは、学習内容が現場のニーズと乖離している場合や、学んだスキルを実践する機会が与えられない場合に起こりやすいです。
対策としては、研修プログラムを設計する段階で、現場の従業員や管理職を巻き込み、実際の業務課題に基づいたカリキュラムを作成することが重要です。
さらに、研修後には、学んだスキルを活用する具体的なミッションやプロジェクトを割り当てる必要があります。
上司が定期的に進捗を確認し、実践の場でフィードバックを行うことで、学習内容の定着を促し、業務への応用を支援する体制を整えるべきです。
育成すべきスキルを具体的に特定できない
経営戦略とリスキリングを結びつける重要性は認識していても、具体的にどのようなスキルを、どの部署の誰に習得させるべきかを特定するのは容易ではありません。
市場の変化が速いため、将来必要となるスキルを正確に予測することが難しいからです。
この課題に対しては、まず全社的に必要とされるデジタルリテラシーのような基礎的なスキルから着手し、従業員全体の底上げを図るアプローチが有効です。
その上で、各事業部門の責任者と連携し、事業戦略の実現に必要な専門スキルを洗い出していく。
社内アンケートやスキルマップを活用して、現状のスキル保有状況を可視化し、目標とのギャップを明らかにすることも、育成すべきスキルを特定する上で役立ちます。
まとめ
本コラムで解説したように、リスキリングはDX時代の企業成長に不可欠な戦略です。
成功事例からは、経営戦略と連動した目的設定、従業員の意欲を引き出す仕組み、そして学習を実践に繋げる機会提供の重要性が読み取れます。
一方で、学習時間の確保やスキルの特定といった課題も存在します。
これらの課題を克服し、自社に合ったリスキリング戦略を構築・実行することが、変化の激しい時代を乗り越え、持続的な競争力を獲得する鍵となります。
他社の取り組みを参考にしつつ、自社の状況に合わせた計画的な導入を進めることが求められます。