最近、注目が集まるリスキリングという言葉をご存知でしょうか?DXに備え、日本企業においてリスキリングの必要性が高まっています。
この記事ではニューノーマル時代において知っておきたいリスキリングの意味や現状、今後の展望を紹介します。
そもそもリスキリングとは?
リスキリングとは、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい職業に就いたり、現在の職業で求められるスキルが大幅に変化したりした際に、必要なスキルを習得することを意味します。
単なる「学び直し」とは異なり、企業の事業戦略に基づいて、将来的に必要となるスキルを計画的に獲得していく点が特徴です。
この言葉の由来は、英語の「reskilling」であり、企業が従業員に新しいスキルを再教育するという文脈で使われます。
リカレント教育やアップスキリングとの違い
リスキリングと混同されやすい言葉に「リカレント教育」と「アップスキリング」があります。
リカレント教育は、働く人がキャリアの途中で一度仕事から離れ、大学などの教育機関で学ぶことを指し、個人の自発的な学びに主眼が置かれます。
一方、アップスキリングは、現在の職務においてより高度な知識やスキルを習得し、専門性を高めることです。
これに対し、リスキリングは企業が主体となり、デジタル化などの事業環境の変化に対応するため、既存の業務とは異なる、新たなスキルを従業員に習得させることを目的とします。
つまり、学ぶ主体、目的、現在の職務との関連性において、これらの言葉はそれぞれ異なるニュアンスを持っています。
なぜ今、多くの企業でリスキリングが推進されているのか
現代においてリスキリングの必要性が高まっている背景には、急速なデジタル技術の進展があります。
AIやIoTといったテクノロジーが普及し、多くの業務が自動化・高度化される中で、従来求められてきたスキルが通用しなくなる一方、新たなデジタルスキルを持つ人材の需要が急増しています。
企業がこの変化に適応し、競争力を維持するためには、従業員のスキルセットを刷新することが不可欠です。
いつ起こるかわからない事業環境の変化に備え、組織全体で計画的に人材育成に取り組む動きが活発化しています。
企業がリスキリングに取り組む4つのメリット
企業がリスキリングを導入することにより、社員のスキルが向上するだけでなく、経営全体に多岐にわたるメリットがもたらされます。
具体的には、専門人材の採用難が続く中での人材不足の解消や、新しい技術の活用による生産性の向上などが挙げられます。
さらに、従業員のキャリア形成を支援することでエンゲージメントを高め、DX推進といった新たな事業展開に向けた強固な組織基盤を構築することも可能です。
ここでは、企業が享受できる4つの主要なメリットを解説します。
既存社員のスキルアップで人材不足を解消できる
近年、DXを推進する上で不可欠なデジタル人材は、多くの企業で需要が高まり、採用競争が激化しています。
外部からの採用だけに頼るのではなく、自社の事業や文化を深く理解している既存社員を育成し、必要なスキルを習得させることで、人材不足を解消できます。
社内でのスキルアップは、採用コストを抑制できるだけでなく、外部人材とのミスマッチのリスクを低減させる効果も期待できます。
既存社員の能力を最大限に引き出すことは、持続的な人材確保の観点からも有効な手段です。
新しい技術の導入で業務生産性が向上する
AIやRPAといった最新技術を導入しても、それを効果的に活用できる従業員がいなければ、期待したほどの成果は得られません。
リスキリングを通じて従業員がこれらの新しいツールやシステムを使いこなすスキルを身につけることで、初めて技術の導入が業務の効率化や自動化に結びつきます。
例えば、データ分析スキルを習得した従業員が、蓄積されたデータを活用して業務プロセスの改善提案を行うといったことが可能になります。
従業員のスキル向上は、結果として組織全体の生産性を高める原動力となります。
従業員のキャリア自律を促しエンゲージメントを高める
会社がリスキリングの機会を提供することは、従業員の成長を支援するという明確なメッセージとなります。
従業員は、自身の市場価値を高めるための学習機会を得ることで、会社への信頼感を深めるとともに、自律的にキャリアを考えるきっかけを得ます。
自身の成長が会社の成長に貢献するという実感は、仕事に対するモチベーションや満足度を高め、組織へのエンゲージメント向上に直結します。
結果として、優秀な人材の離職を防ぎ、定着率を高める効果も期待できます。
DX推進など新たな事業展開の土台が作れる
市場の変化に対応し、企業が持続的に成長していくためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、それに伴う新規事業の創出が不可欠です。
リスキリングによって社内にデジタルスキルを持つ人材を増やすことで、データに基づいた的確な意思決定や、新たなビジネスモデルの構築が可能になります。
全社的にデジタルリテラシーが向上すれば、部門の垣根を越えた協力体制も生まれやすくなります。
このように、リスキリングは変化に対応できる柔軟で強固な組織基盤を作り、未来の事業展開を支える土台となります。

企業でリスキリングを進めるための具体的な6ステップ
リスキリングを成功させるためには、戦略的かつ計画的なアプローチが欠かせません。
場当たり的な研修を実施するだけでは、期待する効果は得られないでしょう。
自社の経営戦略と連動させ、目的を明確にした上で、体系的な手順に沿ってリスキリング施策を進める必要があります。
ここでは、企業がリスキリングを導入し、着実に成果を上げるための具体的な6つのステップを解説します。
この手順を踏むことで、効果的な人材育成を実現できます。
【ステップ1】経営戦略に基づいて必要なスキルを洗い出す
リスキリングの最初のステップは、自社の経営戦略や事業目標を明確に定義することです。
3年後、5年後に会社がどのような姿を目指すのかを具体化し、その目的を達成するために、今後どのようなスキルや知識が必要になるのかを洗い出します。
次に、現状の従業員が保有しているスキルを把握し、将来必要となるスキルとの間に存在するギャップを分析します。
このギャップを埋めるために優先的に習得すべきスキルを特定することが、効果的な学習プログラムを設計するための基礎となります。
【ステップ2】リスキリングの対象者と目標を設定する
必要なスキルが明確になったら、次に誰がそのスキルを学ぶべきかを定めます。
全従業員を対象とする場合もあれば、特定の部署や職種の社員に限定する場合もあります。
対象者を選定する際には、本人のキャリアプランや学習意欲も考慮に入れることが重要です。
対象が決まったら、具体的で測定可能な学習目標を設定します。
「〇〇の資格を取得する」「△△のツールを用いてレポートを作成できるようになる」など、明確なゴールを設けることで、学習者のモチベーションを維持し、進捗を客観的に評価することが可能になります。
【ステップ3】習得スキルに合わせた学習プログラムを設計する
設定した目標を達成するための具体的な学習コンテンツや方法を計画します。
習得すべきスキルの難易度や内容、対象者のレベルに合わせて、eラーニング、集合研修、OJT、読書、ワークショップなど、多様な学習手段を最適に組み合わせることが重要です。
例えば、プログラミングスキルの習得が目的であれば、オンラインのプログラミングスクールと社内での実践プロジェクトを組み合わせるといったリスキリング例が考えられます。
学習期間やカリキュラム、評価方法までを詳細に設計し、体系的なプログラムを構築します。
【ステップ4】学習プログラムを社内に提供し実行する
設計した学習プログラムを対象者に提供し、リスキリングを開始します。
学習の進捗管理やコミュニケーションを円滑にするため、LMS(学習管理システム)などのITツールを活用するのも有効な手段です。
システムを導入することで、管理者は個々の学習状況を把握しやすくなり、学習者は自分のペースで効率的に学習を進められます。
また、学習者が途中で挫折しないよう、上司やメンターによる定期的な面談や、学習者同士が交流できるコミュニティを設けるなど、モチベーションを維持するためのサポート体制を整えることも欠かせません。
【ステップ5】習得したスキルを実践する機会を設ける
研修などで学んだ知識やスキルは、実際の業務で活用して初めて定着し、企業の成果へとつながります。
学習プログラムを終えた従業員に対して、習得したスキルを意図的に使う機会を提供することが極めて重要です。
例えば、データ分析スキルを学んだ社員をマーケティング部門の新しいプロジェクトに配置したり、Webデザインを学んだ社員に社内サイトの改修を任せたりするなど、具体的な業務をアサインします。
実践を通じて成功体験を積むことが、スキルの定着を促し、さらなる学習意欲を引き出します。
【ステップ6】成果を評価しプログラムの改善を繰り返す
リスキリング施策は一度実施して終わりではありません。
施策の効果を客観的に評価し、継続的に改善していくプロセスが不可欠です。
学習プログラム終了後、スキルテストや資格取得状況、業務における行動の変化などを通じて、スキルがどの程度習得されたかを測定します。
また、参加者へのアンケートや上司へのヒアリングを実施し、プログラム内容や運用方法に関するフィードバックを収集します。
これらの評価結果をレポートとしてまとめ、次回のプログラム設計に活かすPDCAサイクルを回すことで、施策全体の質を高めていきます。
リスキリングで活用できる3つの学習方法
リスキリングを実践する上で、どのような学習方法を選択するかは非常に重要です。
企業の予算や育成目標、対象となる従業員の状況などに応じて、最適な手段は異なります。
単一の方法に固執するのではなく、複数のアプローチを組み合わせることで、より高い学習効果が期待できます。
ここでは、多くの企業で採用されている代表的な3つの学習方法を取り上げ、それぞれの特徴やメリットについて解説します。
eラーニングや外部研修サービスを利用する
時間や場所に制約されずに学習を進められるeラーニングは、多忙な従業員でも取り組みやすい方法です。
Schoo(スクー)をはじめとする法人向けサービスでは、ビジネススキルから専門的なITスキルまで、多岐にわたる分野の講座が提供されており、幅広いニーズに対応できます。
また、特定のスキルを短期間で集中的に習得させたい場合は、外部の専門機関が実施する研修に参加させることも有効です。
自社にない専門知識や最新の動向を効率的に学ばせることができ、他社の参加者との交流から新たな視点を得る機会にもなります。
社内でオリジナルの研修プログラムを構築する
自社の具体的な業務内容や企業文化に即した、より実践的なスキルを習得させる場合には、社内で独自の研修プログラムを開発する方法が有効です。
現場の業務に精通した社員が講師を務めることで、教科書的な知識だけでなく、現場で培われたノウハウや暗黙知を直接伝えることができます。
プログラムの構築には相応の工数が必要となりますが、自社の課題解決に直結する人材を育成できるという大きな利点があります。
OJT(On-the-Job Training)と組み合わせることで、学習内容を即座に実践に移し、スキルの定着を促進できます。
外部の専門機関へ社員を派遣する
特に高度な専門性や最先端の技術知識が求められる分野では、大学や大学院、専門の研究機関といった外部の教育機関に社員を派遣する方法が選択肢となります。
社内教育だけでは習得が難しい体系的な知識をじっくりと学ばせることができ、将来の事業を牽引するリーダーや中核的な専門家人材の育成に適しています。
他の学習方法に比べて費用や期間がかかる傾向にありますが、社外の専門家や研究者とのネットワークを構築できるという付加価値も期待できます。
長期的な視点での人材投資として検討されます。
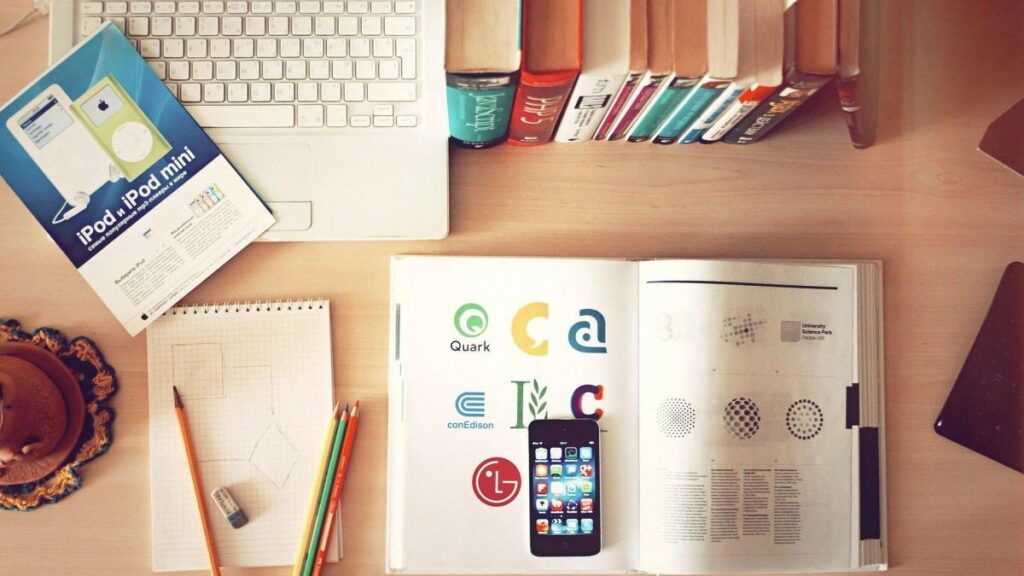
リスキリングを成功に導くための3つのポイント
リスキリングの取り組みは、多大な時間とコストを要するため、その投資を無駄にしないための工夫が求められます。
単に学習プログラムを提供するだけでは、従業員のスキルは定着せず、企業の成果にも結びつきません。
施策を成功に導くためには、いくつかの重要な注意点があります。
ここでは、リスキリングを形骸化させず、組織の力として着実に根付かせるために押さえておくべき3つのポイントを解説します。
なぜリスキリングが必要なのか目的を社員に共有する
リスキリングを推進する上で最も重要なのは、経営層がその目的とビジョンを従業員に明確に伝えることです。
市場環境の変化や会社の将来像を踏まえ、なぜ今、新たなスキル習得が必要なのかを丁寧に説明し、全社的なコンセンサスを形成します。
目的が共有されることで、従業員は学習の意義を理解し、「会社からやらされる」のではなく、自身のキャリアのためにも必要であると捉え、主体的に取り組むようになります。
経営からの力強いメッセージが、従業員の学習意欲を高める土台となります。
業務時間内に学習できる環境を整備する
従業員に学習を促す一方で、通常業務の負担を軽減しなければ、学習時間を確保することは困難です。
リスキリングを自己啓発として従業員個人の努力に委ねるのではなく、企業が責任を持って学習に取り組める環境を整える必要があります。
具体的には、業務時間内に学習時間を設けたり、リスキリング期間中の業務量を調整したりするなどの配慮が求められます。
会社として学習を奨励し、支援する姿勢を明確に示すことが、プログラムへの参加率を高め、学習効果を最大化させる上で不可欠です。
スキル習得を人事評価制度に反映させる
リスキリングへのインセンティブとして、習得したスキルやその後の成果を人事評価や処遇に結びつける仕組みを構築することが有効です。
新たなスキルを身につけ、それを業務で発揮して会社に貢献した従業員が、昇進や昇給といった形で正当に評価される制度があれば、学習へのモチベーションは大きく向上します。
また、スキル習得後のキャリアパスを具体的に示すことで、従業員は学習後の自身の姿をイメージしやすくなります。
評価制度との連動は、リスキリングを一過性のイベントで終わらせず、組織文化として定着させるための鍵です。
リスキリングで価値を生み出す人材になろう
リスキリングはデジタルトランスフォーメーションやリモートワークに象徴されるニューノーマル時代における人材戦略において欠かせない概念です。
技術革新が加速する現代において、リスキリングは企業の持続的成長に不可欠な経営戦略です。
成功の鍵は、経営戦略と連動した目的の明確化、従業員の主体性を引き出す環境整備、そして習得したスキルを正当に評価する仕組みの構築にあります。
計画的な手順に沿って施策を実行し、継続的に改善を繰り返すことで、変化に強い組織を作り上げることが可能になります。
時代の変化に適応して価値を創造し続ける人材を生み出す取り組みなので、積極的に取り組んでいきましょう。


