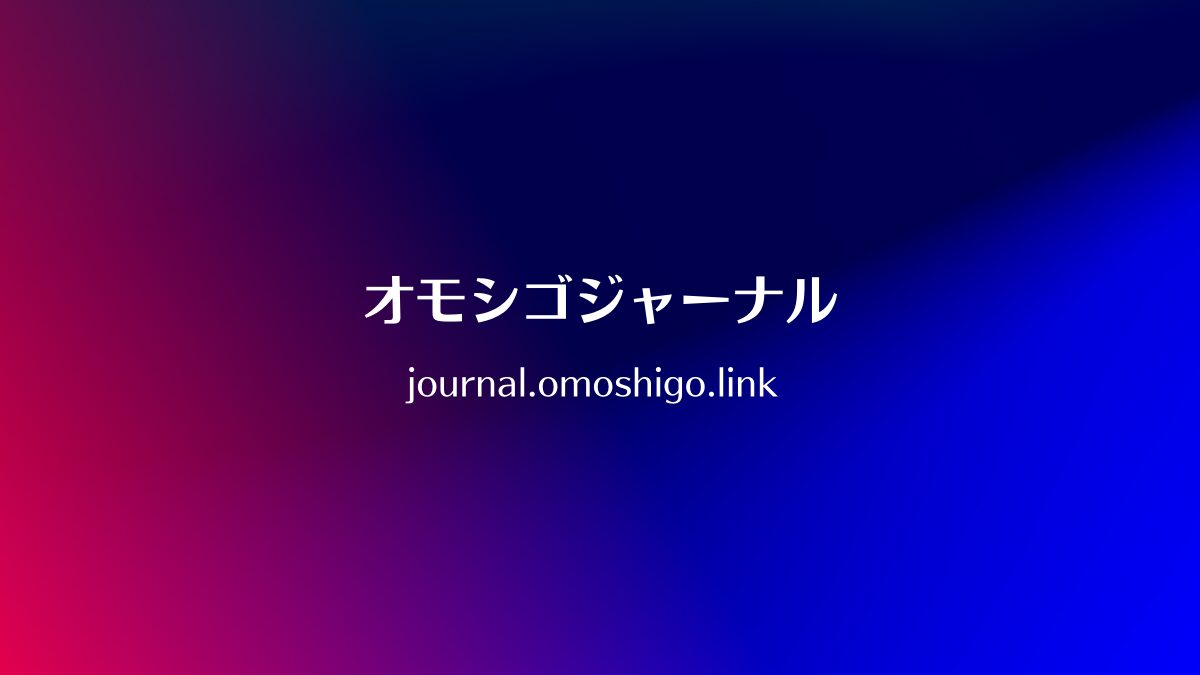DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が企業の競争力を左右する現代において、人材育成の重要性が高まっています。
その解決策として注目されているのが、従業員のスキルを再開発する「リスキリング」です。
リスキリングとは、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、従業員が新しい知識やスキルを習得する取り組みを指します。
この記事では、DX時代におけるリスキリングの必要性から具体的な導入方法、成功のポイント、そして企業の成功事例までを網羅的に解説します。
DX推進に不可欠な「リスキリング」の基本的な意味
リスキリングとは、技術革新やビジネスモデルの変化によって、今後新たに発生する業務に対応するために、既存の従業員に新しい知識やスキルを習得させることです。
特にDXの文脈では、デジタル技術を活用して事業に変革をもたらす人材を育成する取り組みを指します。
これは、社内に存在しないスキルを外部から採用するのではなく、事業内容や企業文化を熟知した従業員を「リスキル」し、育成することを主眼としています。
これにより、企業は変化の激しい時代に迅速に対応し、持続的な成長を目指します。
リスキリングと混同されやすい用語との違い
リスキリングは人材育成に関する様々な用語と混同されることがありますが、その目的や主体には明確な違いがあります。
特に、個人のキャリア形成を主眼とする「リカレント教育」や、既存の知識を捨てることに焦点を当てる「アンラーニング」との違いを理解することは、リスキリングの本質を把握する上で重要です。
これらの用語以外にもOJT(On-the-JobTraining)など多様な育成手法が存在しますが、ここでは代表的な用語との違いを明確にし、リスキリングの特性を明らかにします。
「リカレント教育」との相違点
リカレント教育とは、学校教育を終えて社会に出た後も、個人の意思で教育機関に戻り、必要なタイミングで学び直すことを指します。
リスキリングとの最も大きな違いは、その主体と目的にあります。
リカレント教育が個人主体の自発的な学習であり、個人のキャリア形成を主目的とするのに対し、リスキリングは企業が事業戦略の一環として主導し、DX推進といった企業の変革に必要なスキル習得を目的とします。
そのため、学習内容もリカレント教育が幅広い教養を含む場合があるのに対し、リスキリングは事業のデジタル化など、より実践的で業務に直結した内容に特化する傾向があります。
「アンラーニング」との相違点
アンラーニングとは、既存の知識やスキル、価値観が時代や環境に合わなくなった際に、それらを意図的に捨て去り、新しい知識を吸収する学習法を指します。
リスキリングが新しいスキルを追加することに主眼を置くのに対し、アンラーニングは古い知識を棄却するプロセスを重視する点に違いがあります。
ただし、両者は相反するものではなく、むしろ補完関係にあります。
DXのような大きな変革期には、過去の成功体験や固定観念をアンラーニングした上で、リスキリングによって新たなデジタルスキルを習得することが、より効果的な変革につながります。
DX時代にリスキリングが重要視される3つの背景
近年、多くの企業でリスキリングへの注目が急速に高まっています。
この背景には、デジタル化の波がもたらす深刻な人材不足や、予測困難なビジネス環境の変化といった複合的な要因が存在します。
また、経済産業省をはじめとする政府機関もDX人材の育成を重要な政策課題と位置づけ、企業の取り組みを後押ししています。
ここでは、なぜ今リスキリングが重要視されているのか、その具体的な3つの背景について掘り下げていきます。
深刻化するデジタル人材の不足を解消するため
多くの企業がDXを推進する上で、AIやデータサイエンスといった先端技術を扱えるデジタル人材の不足という課題に直面しています。
これらの専門人材は採用市場での競争が激しく、外部からの獲得は容易ではありません。
そこで、自社の事業内容や業務を熟知した既存の従業員に対し、リスキリングを通じてデジタルスキルを習得させるアプローチが有効な解決策となります。
外部の研修やオンライン講座の活用、関連資格の取得支援などを通じて社内人材を育成することで、企業は外部環境に左右されずに、持続的にDXを推進するための人材基盤を構築することが可能になります。
ビジネス環境の急速な変化に対応するため
現代はVUCA時代とも呼ばれ、市場のニーズやテクノロジー、競合環境が目まぐるしく変化しています。
このような状況下で企業が持続的に成長するためには、組織全体が変化に迅速かつ柔軟に対応できる能力を持つことが不可欠です。
リスキリングは、従業員が保有するスキルを常に最新の状態にアップデートし、陳腐化を防ぐための重要な取り組みです。
従業員一人ひとりが新しい知識や技術を継続的に学ぶ文化を醸成することで、組織全体の変化対応力が高まり、新たなビジネスチャンスの創出や競争優位性の維持につながります。
政府による個人のキャリアアップ支援が強化されているため
政府もリスキリングを重要な政策課題と捉え、企業や個人の取り組みを支援する制度を拡充しています。
経済産業省は「デジタル人材育成プラットフォーム」を通じて学習コンテンツの情報を提供し、厚生労働省は「人材開発支援助成金」によって企業の研修費用の一部を助成しています。
これらの公的支援を活用することで、企業はコスト負担を軽減しながら、質の高いリスキリングプログラムを導入することが可能です。
国を挙げた支援体制が整いつつあることも、企業がリスキリングに踏み出しやすくなっている大きな要因の一つです。
企業がDX推進のためにリスキリングを導入する5つのメリット
リスキリングは、単にデジタル人材の不足を補うためだけの施策ではありません。
DX推進を目的としたリスキリングの導入は、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。
採用コストの削減や生産性の向上といった直接的な効果はもちろん、イノベーションの創出や従業員のエンゲージメント向上など、組織の根幹を強くする効果も期待できます。
ここでは、リスキリングが企業にもたらす5つの具体的なメリットについて解説します。
新たな事業やイノベーションの創出につながる
既存の従業員がデジタル技術やデータ分析といった新しいスキルを習得することで、社内に新たな視点や発想が生まれます。
自社の事業や顧客を深く理解している人材が最新のテクノロジーを手にすることで、既存事業の課題解決や業務プロセスの抜本的な改善だけでなく、これまでにない新しいサービスやビジネスモデルを創出する可能性が高まります。
また、部署を横断して共通のデジタルスキルを持つ人材が増えることで、部門間の連携が促進され、組織的なイノベーションが生まれやすい土壌が育まれます。
採用コストを抑えつつ必要な人材を確保できる
高度な専門性を持つデジタル人材の採用は、獲得競争の激化により多額のコストを要します。
また、外部から採用した人材が自社の企業文化や事業内容に馴染めないというミスマッチのリスクも伴います。
リスキリングは、これらの採用コストやリスクを大幅に低減する有効な手段です。
自社のビジネスを熟知している既存の従業員を育成するため、育成後すぐに即戦力として活躍することが期待でき、定着率も高まる傾向にあります。
これにより、企業はコストを抑えながら、着実にDX推進に必要な人材を確保できます。
従業員のスキルアップにより生産性が向上する
従業員がRPAやBIツールなどのデジタルツールを使いこなせるようになると、これまで手作業で行っていた定型業務の自動化や、データに基づいた迅速な意思決定が実現します。
これにより、業務の効率は飛躍的に向上し、従業員はより付加価値の高い創造的な仕事に時間を振り向けることが可能になります。
また、リスキリングを通じて従業員個々の問題解決能力や業務遂行能力が高まることも、組織全体の生産性向上に直結します。
個人の成長が組織の成長に貢献する好循環を生み出す効果が期待できます。
従業員のエンゲージメントを高める効果がある
企業が従業員のスキルアップやキャリア形成に投資する姿勢は、従業員の会社に対する信頼感や愛着を深めます。
自身の市場価値を高める学習機会が提供されることで、仕事へのモチベーションが向上し、組織への貢献意欲、すなわちエンゲージメントが高まります。
エンゲージメントの高い従業員は、自律的に業務改善に取り組むなど、より積極的に仕事に関わる傾向があります。
結果として、生産性の向上や離職率の低下にもつながり、組織全体の活性化が促進されます。
自律的に行動できる人材が育つ
リスキリングのプロセスでは、従業員が自らのキャリアを見つめ直し、何を学ぶべきかを主体的に考える機会が増えます。
このような経験を通じて、指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決策を探求する自律的な姿勢が養われます。
新しいスキルを習得することで得られる成功体験は自信につながり、従来のやり方にとらわれずに、より良い方法を自ら提案し実行する力も育ちます。
リスキリングは単なる技術習得にとどまらず、変化の激しい時代を乗り越えるために不可欠な、自律型人材の育成にも貢献します。
リスキリング導入前に知っておきたい3つの課題
リスキリングは企業に多くのメリットをもたらしますが、その導入と推進は決して平坦な道のりではありません。
計画を立てる前に、想定される課題を正しく認識し、事前に対策を講じることが成功の鍵となります。
多くの企業が直面しやすい課題として、プログラム導入に伴うコスト、従業員の学習意欲の維持、そしてスキルを習得した人材の流出リスクが挙げられます。
ここでは、これらの3つの代表的な課題について解説します。
学習プログラムの選定や導入にコストがかかる
効果的なリスキリングを実施するためには、一定の金銭的・時間的コストが発生します。
外部の研修サービスやeラーニングプラットフォームの利用料、専門家を講師として招聘する際の費用、教材費などが直接的なコストとして挙げられます。
加えて、従業員が就業時間内に学習する場合、その間の人件費も考慮に入れる必要があります。
これらのコストを投資と捉え、長期的な視点で費用対効果を慎重に見極めることが求められます。
助成金制度などを活用し、負担を軽減する工夫も重要です。
従業員の学習意欲を維持するのが難しい
従業員は日々の業務に追われているため、学習時間の確保自体が大きな負担となることがあります。
また、学ぶ目的やメリットが不明確であったり、学習内容が自身の業務と直接関連しないと感じられたりすると、モチベーションは著しく低下します。
学習意欲を維持するためには、なぜそのスキルが必要なのかを経営層から丁寧に説明し、個々のキャリアプランと結びつけることが重要です。
また、学習の進捗を可視化したり、仲間と学び合えるコミュニティを形成したりするなど、継続を支援する仕組み作りも効果的です。
スキルを習得した人材が離職するリスクがある
企業がコストと時間をかけて従業員を育成した結果、その従業員の市場価値が高まり、より良い条件を求めて他社へ転職してしまうというリスクが存在します。
この人材流出のリスクを最小限に抑えるためには、習得したスキルを正当に評価し、処遇に反映させる仕組みが不可欠です。
例えば、昇進や昇給、新たな職務への配置転換など、スキルを活かせる機会とそれに見合った報酬を提供することが重要になります。
従業員が自社でキャリアを築き続けたいと思えるような魅力的な環境を整備する必要があります。
企業でリスキリングを導入するための5ステップ
リスキリングを成功させるには、場当たり的な取り組みではなく、経営戦略に基づいた体系的なアプローチが不可欠です。
自社の目指す方向性を明確にし、そこから逆算して必要な人材像とスキルを定義、計画的に育成を進める必要があります。
ここでは、効果的にリスキリングを導入し、着実に成果へつなげるための具体的な5つのステップを解説します。
この手順に沿って進めることで、投資対効果の高い人材育成が実現可能になります。
ステップ1:経営戦略から必要なスキルを明確にする
リスキリングの最初のステップは、自社の経営戦略や事業計画と連動させることです。
まず、DX推進によって「何を成し遂げたいのか」というビジョンを具体化し、その実現のためにどのような職務や役割が必要になるかを定義します。
次に、それらの職務を遂行するために不可欠なスキル(例:データ分析、AI活用、クラウド技術、UI/UXデザインなど)を具体的にリストアップします。
この段階で目的とゴールが明確になっていなければ、その後の施策が的外れなものになってしまうため、最も重要なプロセスとなります。
ステップ2:従業員の既存スキルを把握・可視化する
次に、従業員が現在どのようなスキルをどの程度のレベルで保有しているのかを正確に把握します。
スキルマップやタレントマネジメントシステムといったツールを活用し、従業員一人ひとりのスキル、経験、資格などをデータとして収集・可視化することが有効です。
この作業により、ステップ1で定義した「あるべきスキル」と「現状のスキル」とのギャップが全社的、あるいは部署・個人単位で明確になります。
このギャップ分析の結果が、誰にどのような教育プログラムを提供すべきかを判断するための客観的な根拠となります。
ステップ3:目標に合わせた教育プログラムを選定する
スキルギャップが明らかになったら、それを埋めるための最適な教育プログラムを選定・設計します。
学習方法には、eラーニング、集合研修、ワークショップ、OJT(実務を通じた育成)、外部の専門講座への参加など、多様な選択肢があります。
育成対象者の現在のスキルレベル、職務内容、学習のしやすさなどを考慮し、これらの手法を効果的に組み合わせることが重要です。
例えば、基礎知識のインプットにはeラーニング、実践的なスキルの習得にはワークショップやOJTといったように、目的に応じて最適な学習方法を選択します。
ステップ4:学習に集中できる環境を整備し実行する
優れた教育プログラムも、従業員が安心して学習に取り組める環境がなければ成果につながりません。
企業は、従業員が通常業務と学習を両立できるよう、具体的な支援策を講じる必要があります。
例えば、就業時間の一部を自己学習の時間として制度化したり、プロジェクトの合間に学習に専念できる期間を設けたりするなど、時間的なサポートが考えられます。
また、学習費用を会社が負担することはもちろん、上司が部下の学習を後押しするような声かけや面談を行うなど、学習を奨励する文化を醸成することも重要です。
ステップ5:学んだスキルを活かせる実践の場を用意する
リスキリングの最終目的は、スキルを習得することではなく、習得したスキルを業務で活用し、企業の成果につなげることです。
研修などで学んだ知識は、実践で使わなければすぐに忘れ去られてしまいます。
そのため、学習後には、習得したスキルを試せる具体的な業務やプロジェクトを意図的に用意することが不可欠です。
例えば、データ分析研修の受講者を実際のデータを用いたマーケティング分析プロジェクトに任命するなど、インプットとアウトプットのサイクルを回すことで、スキルの定着と応用力の向上が図れます。
リスキリングを成功に導くための4つのポイント
リスキリングを導入するためのステップを着実に実行することに加え、いくつかの重要なポイントを押さえることで、施策の効果を最大化し、成功の確率を高めることが可能です。
従業員の主体性をいかに引き出すか、会社としてどのような支援体制を築くか、そして努力が報われる仕組みをどう作るかが鍵となります。
ここでは、リスキリングを形骸化させずに成功へと導くための4つの要点について解説します。
従業員が自発的に学びたくなる動機付けを行う
リスキリングは、会社からの一方的な命令ではなく、従業員が自らの意思で取り組むことが理想です。
そのためには、学ぶことのメリットを従業員自身が実感できるような動機付けが不可欠になります。
経営層が自社の将来ビジョンとリスキリングの重要性を繰り返し語りかけることに加え、スキル習得が自身のキャリアパスや市場価値の向上にどうつながるのかを具体的に示すことが効果的です。
また、スキルアップを果たした社員をロールモデルとして紹介し、成功事例を共有することも、他の従業員の学習意欲を刺激します。
学習時間や費用面で会社がサポート体制を整える
従業員の学習意欲を具体的な行動につなげるためには、会社側の積極的なサポートが欠かせません。
多くの従業員にとって、学習の障壁となるのは時間と費用の問題です。
これに対して、就業時間内での学習を公式に認めたり、eラーニングの受講料や資格取得費用を会社が負担したりする制度を設けることが有効です。
また、多種多様な学習コンテンツにアクセスできるオンラインプラットフォームを提供したり、キャリア相談ができる窓口を設置したりするなど、従業員が学習を始めやすく、続けやすい環境を整える必要があります。
習得したスキルを人事評価に反映させる仕組みを作る
従業員の学習努力が報われなければ、リスキリングへのモチベーションは長続きしません。
新たに習得したスキルや資格を人事評価の項目に加えたり、昇進・昇格の要件に組み込んだりすることで、学習の成果が正当に評価される仕組みを構築することが重要ですす。
スキルレベルに応じて手当を支給する制度なども、学習へのインセンティブとして機能します。
評価制度とリスキリングを明確に連動させることで、会社がどのようなスキルを求めているのかが従業員に伝わり、組織全体でスキルアップを目指す文化が醸成されます。
社内外の研修サービスや専門家を有効活用する
必要とされる教育プログラムを自社だけで開発・提供するのは現実的ではありません。
特に専門性の高いデジタルスキルに関しては、外部の研修サービスやeラーニングコンテンツを積極的に活用するのが効率的かつ効果的です。
外部サービスは最新の動向を反映した質の高いプログラムを多数提供しており、自社のニーズに合ったものを柔軟に選択できます。
一方で、社内の業務に特化した知識やノウハウについては、経験豊富な社員を講師とした社内勉強会なども有効です。
社内外のリソースを戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。
企業のリスキリング導入事例
国内でも多くの企業がリスキリングに積極的に取り組み、成果を上げています。
例えば、ある大手電機メーカーでは、グループ全体の従業員を対象にAIやデータサイエンスの基礎知識を学ぶデジタルリテラシー教育を実施し、全社的なDX推進の土台を築きました。
また、別の総合電機メーカーでは、従来のIT技術者をクラウドやAIの専門家へと転換させるための高度な育成プログラムを導入し、新たな事業創出に貢献する人材を多数輩出しています。
これらの企業に共通するのは、経営トップの強いコミットメントのもと、自社の事業戦略と連動した体系的な人材育成を行っている点です。
まとめ
DX時代の到来により、企業の持続的成長のためには、従業員のスキルを時代に合わせてアップデートし続けるリスキリングが不可欠な経営戦略となっています。
リスキリングは、深刻化するデジタル人材不足への対応策であると同時に、新たなイノベーションの創出、生産性の向上、従業員エンゲージメントの強化といった多様なメリットを企業にもたらします。
その成功には、経営戦略と連動したスキル目標の設定、体系的な導入ステップの実行、そして従業員の学習意欲を引き出す動機付けや支援体制の構築が重要です。