おはようございます!最新のAI技術が私たちの働き方にこれからどんな影響を与えるのか?
今日の注目ニュースをピックアップしてみました!本日の働き方 x AIニュース!
OpenAIがオープンソースに回帰!企業が安全に使える新AI「gpt-oss-120b」「gpt-oss-20b」を公開
OpenAI(オープンエーアイ)という会社が、久しぶりにオープンソース(※無料で誰でも使える)のAIモデルを2つ発表しました。「gpt-oss-120b」と「gpt-oss-20b」という名前のこの新しいAIは、企業が自分たちのコンピューター内だけで使えるので、大切な会社の情報を外部に送らずに済みます。
これは、スマホのアプリを使うときに、データを携帯会社のサーバーに送らずに、自分のスマホだけで全部処理できるようなイメージです。Apache 2.0ライセンス(※商用利用もOKの自由な利用規約)なので、会社が自由にカスタマイズして使うこともできます。
この動きは、AIを使いたいけれど「会社の秘密が外に漏れるのが心配」だった企業にとって大きなチャンスです。金融業界や医療業界など、これまでプライバシーの関係でAI導入をためらっていた分野でも、安心してAIを活用できるようになります。
私たちの働き方にとっても、これは大きな変化です。会社がより安全にAIを導入できるようになれば、日常業務でのAI活用がもっと身近になるでしょう。AIスキルを身につけることで、より効率的で創造的な仕事ができるようになります。
https://venturebeat.com/ai/openai-returns-to-open-source-roots-with-new-models-gpt-oss-120b-and-gpt-oss-20b/AnthropicのClaude Opus 4.1がプログラミングで圧倒的な成績を記録!
Anthropic(アンソロピック)という会社の新しいAI「Claude Opus 4.1」が、ソフトウェアエンジニアリングのベンチマーク「SWE-bench Verified」で74.5%という高得点を記録し、OpenAIのo3モデル(69.1%)やGoogleのGemini 2.5 Pro(67.2%)を上回って1位になりました。これは、AIがプログラマーの仕事をサポートする能力がさらに進化したことを意味します。
Anthropic社は年間経常収益が7ヶ月で1億ドルから50億ドルに急成長しましたが、API収益31億ドルの約半分がたった2社(CursorとMicrosoft GitHub Copilot)に依存しているという脆弱性も抱えています。この「顧客集中リスク」は、1つの契約変更で会社が危機に陥る可能性を示しています。
この記事から学べるのは、AI技術の進歩がプログラミングの世界に大きな変化をもたらしているということです。プログラマーじゃない人でも、AIの助けを借りて簡単なプログラムを作ったり、業務を自動化したりできる時代が来ています。
つまり、プログラミングの知識がなくても、AIツールを使いこなすスキルを身につけることで、今まで「無理だと思っていた作業」ができるようになる可能性があります。同時に、AIの進化スピードが速いため、常に最新技術にキャッチアップし続ける姿勢も大切です。
https://venturebeat.com/ai/anthropics-new-claude-4-1-dominates-coding-tests-days-before-gpt-5-arrives/Cloudflareの非難を受けたPerplexityを擁護する声が続々
AI検索エンジンのPerplexity(パープレキシティ)が、Cloudflare(クラウドフレア)という会社から「ルール違反をしている」と名指しで批判されましたが、一方でPerplexityを擁護する声も上がっています。これは、AIによる情報収集が「グレーゾーン」にある複雑な問題だからです。
まるで、図書館の本を勝手にコピーして配るのは良くないけれど、「みんなが知りたい情報をまとめて教えてあげる」のは悪いことなのか?という議論に似ています。AIエージェント(※人間の代わりに情報を集めてくれるAI)の利用が広がる中で、こうした議論は今後もっと活発になると予想されます。
このニュースは、私たちがAIツールを使う時に「技術的にできること」と「倫理的に正しいこと」のバランスを考える大切さを教えてくれます。AIを業務で活用する際は、便利さだけでなく、情報の出典や利用ルール、著作権なども意識する必要があります。
これからの時代、AIと上手に付き合うためには、技術的なスキルと同じくらい「AIの正しい使い方」を理解することが重要になります。

世界初の包括的AI法「EU AI Act」が段階的に施行開始
ヨーロッパ連合(EU)が制定した世界で初めてのAIに関する包括的な法律「EU AI Act」が、2024年8月1日から段階的に施行を開始しました。この法律は、AI技術の革新を促進しつつ、その利用の公平性と安全性を確保することを目的としています。
注目すべきは、2025年8月2日から「システミックリスクを持つ汎用AI(GPAI)モデル」に対する規制が適用されたことです。これには、AnthropicやGoogle、Meta、OpenAIなどの大手AI企業が含まれます。違反した場合の罰金は最大3500万ユーロ(約55億円)または世界年間売上高の7%のいずれか高い方という厳格な内容です。
興味深いのは、企業の反応が分かれていることです。Metaは自主的な行動規範への署名を拒否し「ヨーロッパは間違った道を歩んでいる」と批判しました。一方、GoogleやMicrosoft、OpenAIなどは署名に同意しています。
このニュースは、AIがもはや「技術の問題」だけでなく「社会の問題」として扱われる時代に入ったことを示しています。日本で働く私たちにとって、AIを活用する際には技術的なスキルと同じくらい、法的・倫理的な側面を理解することが重要になります。
「AIを使える人」から「AIを適切に、責任を持って使える人」へとレベルアップすることが、これからの時代のビジネスパーソンに求められる資質になるでしょう。

DeepMindの新技術「Genie 3」がAGIへの道筋を描く
Google DeepMind(ディープマインド)が、最新の「Genie 3」というAI技術を発表しました。これは「世界モデル」と呼ばれる技術で、人間のような汎用的な知能(AGI:Artificial General Intelligence)の実現に向けた重要な一歩だと位置づけられています。
Genie 3は、プロンプト(※AIへの指示文)や画像から、リアルタイムでインタラクティブな3D世界を作り出すことができます。まるで、頭の中で想像した世界を瞬時に目の前に現実として作り出せるような技術です。
この技術は直接的に私たちの働き方を変えるものではありませんが、AI全体の進化スピードが加速していることを示しています。将来的に多くの産業や職種に大きな影響を与える可能性があります。
これからのビジネスパーソンは、AI技術の動向に常にアンテナを張り、自分の専門分野とAIの融合可能性を探ることが重要です。AIが代替しにくい創造性や人間関係構築能力を強化しつつ、新しい技術を積極的に学ぶ姿勢が求められます。

リアルタイム3D世界を生成する「Genie 3」の詳細
同じくDeepMindから発表されたGenie 3についてより詳しい情報です。この技術は、プロンプトや画像からリアルタイムでインタラクティブな3Dシミュレーション世界を生成できます。わずか7ヶ月で大幅に進化し、生成された環境のオブジェクトや天候をリアルタイムで変更することも可能になりました。
この技術は、ゲーム開発への応用も期待されますが、DeepMindはAIエージェントの訓練データ不足を補う研究ツールとして重視しています。現実世界での試行錯誤が困難または高コストな作業を、仮想空間で効率的に行えるようになる可能性があります。
製品設計、都市計画、災害シミュレーションなど、様々な分野でのプロトタイピングや検証プロセスが劇的に変わるかもしれません。将来的には、AIが生成する合成データやシミュレーション環境を活用するスキルが、多くの業界で価値を持つようになるでしょう。
ただし、AIには「幻覚」(※事実でない情報を生成してしまう現象)などの限界もあるため、最終的な判断は人間が責任を持つ意識が大切です。
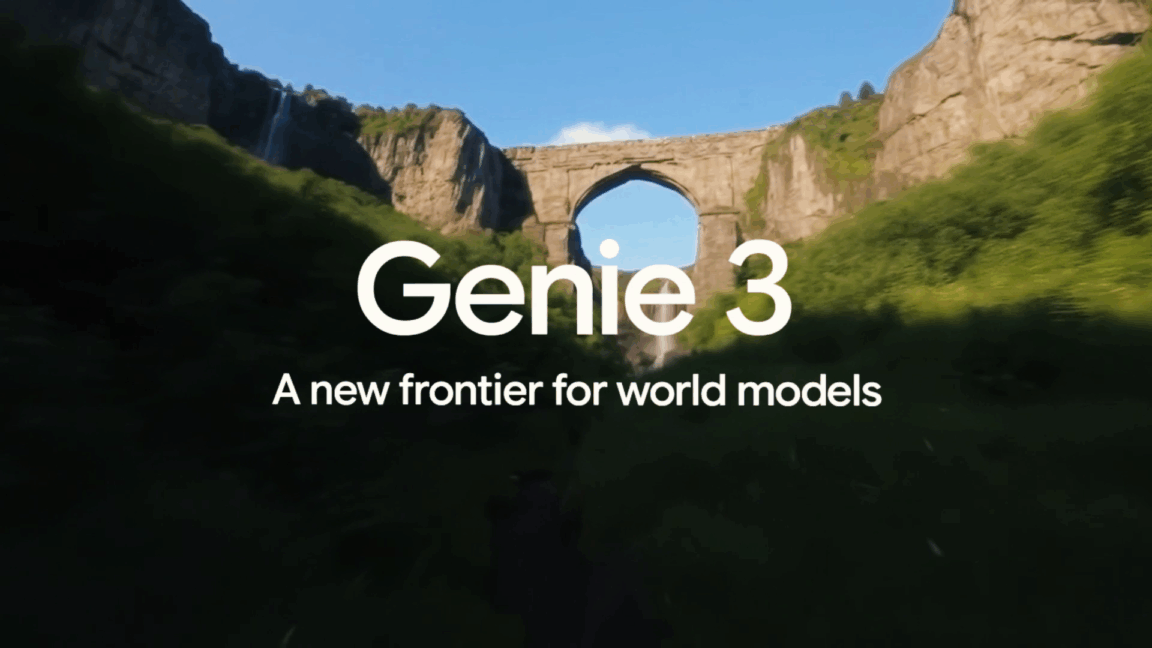
OpenAI vs ニューヨーク・タイムズの法廷バトル
OpenAIとニューヨーク・タイムズ(NYT)の間で、ChatGPTのユーザーチャットログの開示範囲について争いが続いています。OpenAIは2000万件のログで十分と主張していますが、NYTは1億2000万件のログを要求しています。
この争いは、AIサービスを提供する企業が直面する複雑な課題を浮き彫りにしています。データの管理、削除されたデータの取り扱い、法的要請への対応など、技術的にも法的にも難しい問題が山積みです。
私たちがAIツールを使う際にも、機密情報や個人情報を含むチャットの取り扱いには細心の注意を払う必要があります。「便利だから何でも聞いてしまう」のではなく、「どんな情報がどう管理されているか」を意識することが大切です。
企業側も、AIサービスを導入する際には適切なデータガバナンス体制を構築する必要があります。AIの法的・倫理的側面への理解は、今後のビジネスにおいてますます重要になるでしょう。

Google検索のAI劣化に限界!記者が有料検索「Kagi」へ完全移行
Ars Technicaの技術編集者が、Google検索の「AI要約機能の強制表示」と「堂々と間違った情報を事実のように伝える」問題に我慢の限界を迎え、有料検索エンジン「Kagi(カギ)」への完全移行を決断しました。
記者によると、GoogleのAI Overviews(※検索結果の上に表示されるAI要約)は技術的な内容で頻繁に間違いを犯し、しかもそれを「確信を持って」表示します。例えば、サターンVロケットの技術的詳細について、AIが完全に間違った情報を断言していました。一方、Kagiはシンプルに正確な情報源(専門サイト)へ直接誘導してくれます。
Kagiの大きな魅力は「ユーザーがお客様」というビジネスモデルです。年間約100ドル(約15,000円)の料金で、広告もAI要約もなく、Quora(※低品質なQ&Aサイト)やPinterest(※検索ノイズの多い画像サイト)のような迷惑サイトを完全にブロックできます。さらに、検索結果の優先度を自分好みにカスタマイズ可能で、画像検索では右クリックで直接画像保存もできます。
記者は5ヶ月間の本格使用で、「Kagiで見つからずにGoogleに戻った回数は片手で数えられる程度」と高く評価しています。
このニュースは、「無料だから良い」という固定観念を見直すきっかけを与えてくれます。情報収集は現代ビジネスの基本スキルです。検索の品質が下がることで失う時間や、間違った情報に基づく判断のリスクを考えれば、信頼できる有料ツールへの投資は十分に合理的な選択と言えるでしょう。

AIと共に進化する働き方
今日紹介したニュースから見えてくるのは、AIがますます身近になり、私たちの働き方を大きく変えていく可能性です。同時に、技術の進歩と共に新しい課題や選択肢も生まれています。
これからの時代、大切なのは、
AIは私たちの敵ではなく、より創造的で価値ある仕事に集中するためのパートナーです。最新技術の波に乗って、自分らしい働き方を見つけていきましょう!

